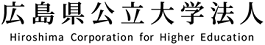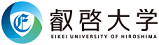本文
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年度履修証明プログラム『Family Reconstruction Support Program(家族再構成支援プログラム)』を開設します
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年度履修証明プログラムの開設について
次のプログラムを開設します。
受講を志望される方は,下記のプログラムの内容,申請方法等を参照のうえ,申請してください。
募集要項はこちらをご覧ください。 募集要項 [PDFファイル/450KB]
プログラム名称
Family Reconstruction Support Program(家族再構成支援プログラム)
実施体制
プログラム責任者:保健福祉学部 保健福祉学科 人間福祉学コース 准教授 大下 由美
このプログラムは、課題を抱えた家族が、問題解決システムとして機能するように支援していくための理論と技術について、実践的に学ぶプログラムで、「家族支援の基礎理論(講義編)」、「家族の問題の評定と介入に関する知識と技術(実践論編)」と「事例に基づく演習(スーパービジョンを含む)(事例編)」の3つの小プログラムから構成されている。
3つの小プログラムの内、「家族支援の基礎理論」と「事例に基づく演習(スーパービジョン)」は、プログラム責任者が単独で実施する。講義編は、学部授業の短縮版であり、内容の一部は、申請者を中心として、大学院博士後期課程の学生(社会人)と協働して展開する場合がある。なお院生が関わる場合も、プログラム申請者が事前に許可した内容であり、申請者同席の元、実施される。
証明書交付に必要な体制として、1年間を通して、3つの小プログラムそれぞれにおける出欠管理、およびレポート提出(演習では逐語記録の提示)内容により評価を行う。なお講義編で外部講師を含んだ場合は、講師陣を含めて総合的に評価する。
目的及び内容等
目的
子どもと家族への福祉の増進(家族の再構成支援)に関与している、地域で核となる専門職員の知識とスキルの向上を図る。
内容
| 回 | 講座概要 |
|---|---|
| 第1回 | 家族支援の基礎理論1 |
| 第2回 | 家族支援の基礎理論2 |
| 第3回 | 家族支援の基礎理論3:変容論 |
| 第4回 | 家族支援の基礎理論4:変容技法論 |
| 第5回 | 家族の問題の評定と介入に関する知識と技術1 |
| 第6回 | 家族の問題の評定と介入に関する知識と技術2 |
| 第7回 | 家族の問題の評定と介入に関する知識と技術3 |
| 第8回 | 家族の問題の評定と介入に関する知識と技術4 |
| 第9回 | 家族の問題の評定と介入に関する知識と技術5 |
| 第10回 | 事例に基づく演習1 |
| 第11回 | 事例に基づく演習2 |
| 第12回 | 事例に基づく演習3 |
| 第13回 | 事例に基づく演習4 |
| 第14回 | 事例に基づく演習5 |
受講期間
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年7月26日(土曜日)~bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载8年6月14日(日曜日)【全14回?総時間数70時間】
受講対象者
以下の(1)及び(2)の条件を満たす者
(1)高等学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力を有する者
(2)児童福祉にかかわる公的機関、福祉施設および事業所等(児童養護施設、子ども家庭センター、 市役所等の子ども家庭課、地域の子育て支援?相談センターの職員等)で、家族再構成支援(親子間の コミュニケーションの改善の支援)に従事している、あるいは関心を持っている実践家
募集人数
5名(申込多数の場合は抽選)
会場
県立広島大学 三原キャンパス(三原市学園町1番1号)
修了要件
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年7月~bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载8年6月までの間で、「家族支援の基礎理論(講義編)」「家族の問題の評定と介入に関する知識と技術(実践論編)」「事例に基づく演習(事例編)」の3つの小プログラムすべてにおいて8割以上出席し、60時間以上の履修をしていること。かつ、レポート及び受講者自身の事例でのスーパービジョンを受けていること。
受講料
26,600円(非課税)
(1日単位の受講はできません。納入後の受講料はいかなる理由があっても返還できません。)
申込方法
下記のQRコードまたは申込フォームから申し込み後、必要書類を郵送してください。

/ques/questionnaire.php?openid=969
申込フォーム入力後、以下(1)~(3)の3点を、書類郵送先へお送りください。(6月6日必着)
(1)【本学様式】履修証明プログラム履修許可願
履修許可願 [Wordファイル/60KB] 履修許可願 [PDFファイル/99KB]
(2)【本学様式】履歴書
履歴書 [Wordファイル/16KB] 履歴書 [PDFファイル/67KB]
(3)最終卒業学校の卒業(卒業見込)証明書
必要書類の本学への到着をもって受講申し込みを受理します。
申し込み後、メールで受講案内および振込案内をお送りします。パソコンからのメール(@pu-hiroshima.ac.jp)が受け取れるよう設定しておいてください。
申込締切
bbin视讯平台_bbin游戏官网¥注册下载7年6月25日(水曜日)
※必要書類の郵送は6月26日(木曜日)必着
書類郵送?問い合わせ先
県立広島大学 三原地域連携センター 履修証明プログラム係
〒723-0053 三原市学園町1番1号
電話 0848-60-1120 (平日9時00分~17時00分)
 大学概要
大学概要
 学部?大学院?専攻科
学部?大学院?専攻科
 学生生活?就職支援
学生生活?就職支援
 研究?地域連携?国際交流
研究?地域連携?国際交流
 入試情報
入試情報